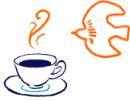1 睡眠薬に対する不安

ひと昔前ほどではないにせよ、今も睡眠薬に対する不安は根強いものがあります。一度使い始めるといつまで飲み続けるかわからず、治療のゴールが見えにくいこと、薬の特性や副作用に対する誤った理解などが不安の根底にあると考えられます。
2 睡眠薬の何が不安?
睡眠薬に対する不安とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。国内で行われた聞き取り調査で、最も多かった回答は「依存性があり止められなくなる」でした。ほかにも「効果がなくなる(量が増える)」という薬が増えることに対する懸念、「翌日に眠気が残る」「大量服用すると死んでしまう」など副作用を不安視している傾向もうかがえました1)。

| 目的: |
日本における睡眠障害(不眠症状を含む)および不眠症状の有症率(又は有病率)、ならびに睡眠改善薬の使用実態とそれに伴うQOLの改善状況を明らかにすること。 |
|---|---|
| 方法: |
全国より層化無作為抽出された4000世帯を訪問し、在宅中の2206人を調査対象とし、面接聞き取り調査法によってデータを取得した。ICSD2ndに基づく不眠症(日中のQOL低下を含む)および不眠症状の頻度、睡眠改善薬の使用頻度を算出し、夜間不眠の改善頻度および日中の不調改善との関連性を検討した。 |
三島和夫. 平成21年度厚生労働科学研究・循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業 統括報告書2012 を元に作成
3 睡眠薬の副作用
睡眠薬の種類を問わず、よく見られる副作用としては、眠気やふらつき、頭痛、倦怠感、精神・運動機能の低下などが挙げられます。特に高齢者の場合、眠気やふらつきは転倒や骨折につながることがあるので注意が必要です。睡眠薬の種類によっては、長期服用により一時的に記憶力や判断力などの認知機能の低下が生じることもありますが、休薬すれば改善します。ただし、回復までに時間がかかる機能もあります2)。
血圧や呼吸をつかさどる脳の部位に強い抑制作用を持つ睡眠薬が使われていた時代は、大量に服用して死亡に至るケースもありました2)。ですが、現在広く使われている睡眠薬を医師の指示を守って服用すれば、このような強い抑制作用はないと考えられています。
4 医師の指示のもと正しく使えば怖くない

副作用があるのは睡眠薬だけに限りません。ほかの薬も同じです。睡眠薬より注意すべき副作用を有する薬もあります。例えば、抗がん剤のように、副作用を軽減するために別の薬を服用しなければならない薬もめずらしくありません。
医師が指示する用法、用量を守って服用していれば、安心して適切な治療を行うことが可能です。仮に副作用が発現したとしても、すぐに医師や薬剤師に相談すれば減量や休薬、別の薬剤への変更など、適切な対応が図られます。
不安が強すぎると緊張のために薬が効きにくくなったり、服薬が不規則になって症状の悪化を招きかねません。その点からも、睡眠薬は必要以上に恐れる薬ではないのです。
また、睡眠薬を恐れて眠れない場合に頓服的に服用する方もいます。しかしながら、慢性不眠症の場合には眠れないままでいると、睡眠薬を服用すれば良いかどうかで悩んでしまい、かえって覚醒度が高くなり眠れなくなる原因ともなります。3か月以上不眠が続く慢性不眠症では、毎晩服用した方が良いことが多いです。
- 1)三島和夫. 平成21年度厚生労働科学研究・循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業 統括報告書2012
- 2)三島和夫 編集:睡眠薬の適正使用・休薬ガイドライン. じほう. P.147-153, 2014